皆さん、こんにちは!中学生の「やよい」です。今日は、日本の伝統行事の中でも少し影が薄くなっている「重陽の節句」についてご紹介します。実は私、先日の国語の授業で五節句について調べる課題が出たとき、ひな祭りや七夕は知っていたのに、この重陽の節句のことをよく知らなかったんです。おじいちゃんに聞いたら、とっても面白いお話をたくさん教えてくれました!

やよい、重陽の節句は昔は今よりもずっと大切にされていた行事なんだよ。菊の花と長寿のご利益が結びついた、とても意味深い節句なんだ
そんなおじいちゃんと一緒に調べた重陽の節句の魅力を、皆さんにお届けします!古代中国から伝わり、日本で独自の発展を遂げたこの素敵な行事のルーツや風習、そして現代での楽しみ方まで、じっくりとご紹介しますね。
重陽の節句の起源と歴史
重陽の節句の意味と由来
重陽の節句って聞いたことありますか?実は五節句の一つで、毎年9月9日に行われる伝統行事なんです。「重陽」という名前の由来は、陰陽五行説における「陽」の数である「9」が重なる日だからなんですよ。
中国の古い暦法では、奇数は陽の数とされていました。その中でも「9」は陽の数の中で最も大きな数。だから9月9日は「陽」が二つ重なる特別な日として、重陽の節句と呼ばれるようになったんです。

おじいちゃん、なんで9が陽の数なの?

昔の人は奇数を陽、偶数を陰と考えていたんだよ。1、3、5、7、9が陽の数で、その中でも9が最も大きいからね
重陽の節句は「菊の節句」とも呼ばれていて、菊の花を愛で、菊酒を飲む習慣がありました。菊には邪気を払い、長寿をもたらす力があると信じられていたんです。日本では平安時代に中国から伝わり、貴族の間で宮中行事として定着していきました。

やよい、昔の人は季節の変わり目に邪気が入りやすいと考えていたんだよ。だから菊の力を借りて、邪気を払っていたんだ

へえ、今でいう免疫力アップみたいな意味もあったんだね!
皆さんも、9月9日が来たら菊の花を飾ってみませんか?昔の人の知恵を現代に生かすのも素敵ですよね。次は、この行事がどのように中国から伝わったのかについて詳しく見ていきましょう。
中国由来の重陽の節句
重陽の節句は、実は中国の古代王朝時代にまで遡る長い歴史を持っています。中国では「重九節」とも呼ばれ、漢の時代(紀元前206年~220年)には既に行われていたという記録があるんです。
中国の伝説では、戦国時代の占い師・費長房(ひちょうぼう)という人が、ある村人に「9月9日に家族を連れて高い山に登り、菊花の酒を飲むように」とアドバイスしました。その村人が言われた通りにしたところ、村に疫病が流行って多くの人が亡くなったのに、山に登った家族だけが助かったという話が伝わっています。

おじいちゃん、本当にそんなことあったの?

伝説だから証明はできないけど、昔の人はこういう物語を通して大切な知恵を伝えていたんだよ
中国では重陽の節句に、次のような習慣がありました:
・高い山に登る(「登高」と呼ばれる)
・菊の花を観賞する
・菊酒を飲む
・重陽糕(ちょうようこう)という特別なお菓子を食べる
これらの習慣は、唐の時代(618年~907年)に日本に伝わり、平安時代には宮中行事として取り入れられました。『源氏物語』や『枕草子』などの古典文学にも重陽の宴の様子が描かれているんですよ。

やよい、日本と中国は海を隔てているのに、文化がこうして伝わっていくのは素晴らしいことだね

うん、今でいうと国際交流だね!
文化の交流は昔から行われていて、それが今の日本文化の豊かさにつながっているんですね。さて、次は古代の日本人がこの行事をどのように受け入れ、どんな意義を見出していたのか見ていきましょう。
古代から続く重陽の節句の意義
平安時代、重陽の節句は宮中で盛大に祝われる重要な行事でした。『延喜式』という平安時代の法令集には、重陽の節句の儀式について詳しく記されています。貴族たちは美しい装いで宮中に集まり、菊を観賞しながら詩歌を詠み、菊酒を飲んで長寿を祈願したのです。
特に注目すべきは、重陽の節句が単なる季節の行事ではなく、厄除けや長寿祈願という明確な目的を持っていたことです。9月は季節の変わり目で、昔の人々は病気にかかりやすい時期と考えていました。そこで菊の力を借りて邪気を払い、健康を祈ったのです。

おじいちゃん、平安時代の人も季節の変わり目に体調を崩しやすかったんだね。今と同じなの

そうなんだよ。自然と共に生きていた昔の人は、季節の変化に敏感だったんだ
江戸時代になると、重陽の節句は武家社会でも大切にされるようになりました。将軍家では菊の節句に合わせて菊の花を飾り、菊見の宴を催しました。徳川家康は特に菊を愛し、菊の紋を家紋にしたことでも知られています。
また、一般庶民の間でも、重陽の節句には菊の花を浮かべたお風呂に入る「菊湯」の習慣や、菊の花びらを浮かべた酒を飲む風習が広まりました。これらは全て、菊に宿る力で邪気を払い、長寿を願う心からきているのです。

やよい、江戸時代の人々は自然の力を生活に取り入れる知恵を持っていたんだよ

現代の私たちも見習うべきことがたくさんあるね!
五節句の中で少し影が薄くなってしまった重陽の節句ですが、季節の変わり目に健康を祈る意義は今も変わりません。次は、重陽の節句にまつわる興味深い伝承や神話について掘り下げてみましょう。
重陽の節句にまつわる伝承と神話
重陽の節句と長寿祈願の伝説
重陽の節句と長寿には、深い結びつきがあります。その背景には様々な伝説が息づいています。最も有名なのは、先ほども少し触れた中国の費長房(ひちょうぼう)の伝説です。この物語は「黄花の節句」という別名の由来にもなっているんですよ。
伝説では、占い師の費長房が弟子の桓景(かんけい)に、「9月9日には必ず家族を連れて高い山に登り、菊花酒を飲むように」と忠告しました。桓景がその通りにしたところ、家に残した家畜や鶏が全て死んでいて、赤い血が流れていたといいます。費長房は災いが起きることを予知していたのです。

おじいちゃん、なんで菊のお酒が災いから守ってくれるの?

菊には特別な力があると信じられていたんだよ。菊の香りには邪気を払う効果があるとされていたんだ
日本にも、菊にまつわる長寿伝説があります。昔話「竜の口の菊水」では、菊の露を飲んだ村人が病気知らずの長寿を得たという話が伝わっています。また、伊豆の「菊池」の水は菊の力で若さを保つとされ、鎌倉時代の武将たちが争った逸話も残っています。
さらに、菊の花は日本の皇室の紋章にも使われるほど尊ばれてきました。16弁の菊の花「菊花紋章」は、太陽を象徴し、永遠の命と繁栄を表しているとされています。

やよい、日本人は古くから菊を特別な花と考えていたんだね

うん、皇室の紋章になるくらいだから、本当に大切にされてきたんだね!
このように、重陽の節句には長寿と健康を願う人々の切なる思いが込められています。皆さんも、菊の花を見かけたら、その花に込められた長い歴史と伝説に思いを馳せてみてくださいね。次は、日本独自の重陽の行事と神話について探っていきましょう。
日本独自の重陽行事と神話
中国から伝わった重陽の節句ですが、日本では独自の発展を遂げました。特に平安時代から鎌倉時代にかけて、日本ならではの行事や伝承が生まれていったのです。
日本独自の風習として特徴的なのが「菊合わせ」です。これは貴族たちが美しい菊の花を持ち寄り、その美しさを競うという雅な遊びでした。『源氏物語』の「藤袴」の巻にも、光源氏が菊合わせを楽しむ様子が描かれています。

おじいちゃん、今でいう花のコンテストみたいなものだね

そうだね。ただし単に美しさを競うだけでなく、花に詩歌を添えて風情を楽しむ文化的な側面も強かったんだよ
また、日本では重陽の節句に「曲水の宴」も行われました。蛇行する小川のほとりに座り、上流から流れてくる盃が自分の前を通るまでに和歌を詠むという雅な遊びです。これも中国から伝わりましたが、日本では特に重陽の行事として定着しました。
神話的な側面では、菊の花は不老不死の象徴とされました。伝説の蓬莱山には菊の露を含んだ泉があり、それを飲むと永遠の命を得られるという物語も伝わっています。
興味深いのは、日本では重陽の節句が神道の祭祀とも結びついたことです。奈良県の石上神宮では、重陽の日に「菊花祭」が行われ、神前に菊を供えて国家の安泰と五穀豊穣を祈願します。

やよい、日本人は外国から入ってきた文化を、日本の風土や考え方に合わせて上手に取り入れてきたんだよ

日本らしさを大切にしながら新しいものを取り入れるって、すごく素敵な文化だね
このように、重陽の節句は日本独自の美意識や神道信仰と融合しながら発展してきました。和と洋が調和する日本文化の素晴らしさを感じますね。次は、重陽の節句の主役である菊の花の効能と役割について見ていきましょう。
重陽の節句における菊の効能と役割
重陽の節句の主役である菊の花には、古来より様々な効能が期待されてきました。菊が単なる観賞用の花ではなく、実用的な価値も持つ植物として重宝されてきた理由を探ってみましょう。
まず注目すべきは、菊の薬効です。中国の古い医学書『神農本草経』には、菊が「百病を治し、五臓を利し、目を明るくし、身を軽くし、寿命を延ばす」と記されています。実際、食用菊には解毒作用やビタミンCが豊富なことが現代の科学でも確認されているんですよ。

おじいちゃん、昔の人は科学的な分析もないのに、どうやって菊の効能を知ったの?

長い時間をかけた経験の積み重ねだよ。昔の人の知恵は侮れないんだ
重陽の節句では、菊の花を浮かべた風呂「菊湯」に入る習慣がありました。菊の香りや成分が湯に溶け出し、肌に付着することで邪気を払い、若さを保つと信じられていたのです。また、菊枕といって、菊の花を詰めた枕も重陽の節句の風習で、これを使うと目の病気が治るとされていました。
最も有名なのは「菊酒」でしょう。菊の花びらを日本酒に浮かべて飲むこの風習は、現代でも残っています。菊酒を飲むことで長寿を得られるという信仰があり、宮中の重陽の宴では欠かせないものでした。

やよい、昔の人は菊を見て『美しいな』と思うだけでなく、その力を生活に活かす知恵を持っていたんだね

今でいうホリスティックな考え方みたいだね。美しさと実用性を両立させていたなんて素敵!
菊の花言葉は「高潔」「高貴」「長寿」。その美しさだけでなく、私たちの健康を守る力も持つ菊の花は、まさに重陽の節句にふさわしい花と言えますね。皆さんも今年の重陽の節句には、菊の花の力にあやかってみませんか?次は、今日でも楽しめる重陽の節句の伝統的な祝い方と風習について詳しく見ていきましょう。
重陽の節句の伝統的な祝い方と風習
重陽の節句の祝い方ガイド
重陽の節句を現代に甦らせてみませんか?昔ながらの風習を取り入れつつ、今の生活にマッチした祝い方をご紹介します。9月9日、ぜひ家族や友人と一緒に日本の伝統行事を楽しんでみてください。
まず基本は、菊の花を飾ること。玄関や居間に色とりどりの菊の花を活けるだけで、重陽の節句の雰囲気が生まれます。食用菊なら、お浸しやてんぷらにして食卓に並べるのもおすすめです。

おじいちゃん、食用菊って普通のお花屋さんで売ってるの?

スーパーの野菜売り場や農産物直売所で『食用菊』として売られているよ。もみじおろしと一緒に食べると美味しいんだ
高い場所に登るという風習も現代風にアレンジできます。高い山に登るのが難しければ、展望台や高層ビルに行くのも良いでしょう。高いところから景色を眺め、邪気を払う気持ちで深呼吸すれば、心もすっきりするはずです。
家族で楽しむなら、菊の押し花づくりはいかがでしょうか?菊の花を押し花にして栞やカードを作れば、重陽の節句の素敵な記念になります。子どもたちも喜んで参加してくれるでしょう。
お酒が好きな大人なら、菊酒を楽しむのがおすすめ。食用菊の花びらを日本酒に浮かべるだけで立派な菊酒に。「長寿を願って」と杯を交わせば、特別な一日になりますよ。

やよい、昔の人は季節ごとの行事を大切にして、メリハリのある生活を送っていたんだね

今の私たちこそ、こういう季節の行事を大切にするべきかもしれないね!
重陽の節句は、家族の健康と長寿を願う素晴らしい機会です。皆さんも今年の9月9日は、少し特別な一日として過ごしてみませんか?次は、重陽の節句を彩る菊酒について、より詳しくご紹介します。
菊酒を楽しむ重陽の節句
重陽の節句を語るうえで欠かせないのが「菊酒」です。菊の花びらを浮かべた酒は、単なる飲み物以上の意味を持ち、長い歴史と深い文化的背景を持っています。
菊酒の起源は古代中国にさかのぼります。先ほどお話しした費長房の伝説にもあるように、菊酒には邪気を払い、長寿をもたらす力があると信じられていました。日本には奈良時代から平安時代にかけて伝わり、特に貴族の間で重陽の宴に欠かせない飲み物となりました。

おじいちゃん、菊酒って本当に効果があるの?

菊には抗酸化作用があるし、菊の香りにはリラックス効果もあるよ。でも何より大切なのは、伝統を継承する気持ちかもしれないね
菊酒の作り方は意外と簡単です。まず食用菊の花びらをきれいに洗い、日本酒に浮かべるだけ。花びらから芳香成分が溶け出し、ほのかに菊の香りのする美しい酒になります。菊の品種によって風味が変わるので、いろいろ試してみるのも楽しいですよ。
江戸時代には、菊酒に砂糖や蜂蜜を加えた「菊見酒」も人気でした。菊の展示会で楽しむお酒として、市民の間でも親しまれていました。当時の錦絵には、菊見酒を片手に菊を鑑賞する人々の様子も描かれています。
現代では、9月9日に菊酒を楽しむ風習は一般家庭ではあまり見られなくなりましたが、日本酒の蔵元によっては重陽の節句に合わせて特別な菊酒を販売するところもあります。また、京都の料亭や老舗旅館では、9月になると重陽の節句の特別メニューとして菊酒を提供するところもあるんですよ。

やよい、伝統って形を変えながらも続いていくものなんだね

うん、古い風習も現代風にアレンジすれば、もっと身近に感じられるね!
皆さんも今年の重陽の節句には、ぜひ菊酒に挑戦してみませんか?もちろん、お酒が飲めない方や子どもたちは、菊の花びらを浮かべた白湯やジュースでも楽しめますよ。次は、重陽の節句に関連する季節行事や全国の名所について見ていきましょう。
重陽の節句の季節行事と名所
重陽の節句の時期には、全国各地で菊にまつわる様々な行事や祭りが開催されます。歴史と伝統を今に伝えるこれらのイベントは、まさに日本文化の宝とも言えるでしょう。
最も有名なのは、皇居東御苑で毎年11月上旬に開催される「菊花展」です。宮内庁の菊栽培技術の粋を集めた見事な菊の数々が展示され、中でも1本の茎から数百の花を咲かせる「千輪咲き」や、人形を菊で装飾した「菊人形」は圧巻です。

おじいちゃん、皇居の菊花展って見に行けるの?

もちろん一般公開されているよ。秋の東京観光なら、ぜひ足を運んでみるといいね
愛知県の名古屋城でも、10月下旬から11月中旬にかけて「名古屋城菊花大会」が開催されます。豪華な菊の花壇や奉献菊など、400年の歴史を持つ由緒ある菊花展です。名古屋城の金の鯱と菊の華やかさのコントラストは、まさに秋の風物詩となっています。
福岡県太宰府市では、9月9日に太宰府天満宮で「重陽神事」が行われます。菅原道真公の誕生日でもあるこの日、菊の花を供えて学問の神様を祀ります。受験生なら、ぜひお参りしたい神事ですね。
また、奈良県飛鳥村の石舞台古墳周辺では「飛鳥の石舞台と彼岸花まつり」が9月中旬から下旬に開催されます。重陽の節句の時期にちょうど見頃を迎える彼岸花と古墳のコラボレーションは、まさに秋の絶景です。

やよい、日本各地にある行事を訪ねて回るのも素敵な旅になるね

うん!来年の重陽の節句は、どこかのお祭りに行ってみたいな!
全国各地で開催される菊にまつわる行事は、日本人が古くから菊を愛でてきた証でもあります。季節の移ろいを感じながら、重陽の節句ゆかりの場所を訪ねてみてはいかがでしょうか?次は、重陽の節句と日本の伝統文化との深いつながりについて見ていきましょう。
重陽の節句と文化に息づく要素
重陽の節句と日本の伝統文化
重陽の節句は、日本の伝統文化の様々な側面と密接に結びついています。その影響は文学、美術、音楽、そして年中行事など広範囲に及んでいるのです。
まず特筆すべきは、和歌や俳句などの文学における菊のモチーフです。『古今和歌集』や『新古今和歌集』には菊を詠んだ和歌が数多く収められています。松尾芭蕉の「菊の香や奈良には古き仏たち」という句は、菊の香りと奈良の古い仏像を重ね合わせた名句として知られています。

おじいちゃん、なんで昔の人はそんなに菊を詠んだの?

菊は秋を代表する花で、その美しさと香りが詩心を刺激したんだよ。菊に長寿のイメージがあったことも大きいだろうね
絵画の世界でも菊は重要なモチーフでした。特に琳派の尾形光琳や酒井抱一は、金地に菊を描いた豪華な屏風絵を残しています。また、浮世絵師の歌川広重や葛飾北斎も、秋の風物詩として菊を描いた作品を多く残しています。
茶道においても、重陽の節句は重要な季節の区切りとして認識されていました。9月の茶会では、菊をモチーフにした菓子や、菊の花を浮かべた菊湯が供されることがあります。茶室に飾る茶花としても菊は珍重され、侘び寂びの美学と結びついています。
能楽にも菊をテーマにした演目があります。「菊慈童」は、伝説の不老不死の少年・菊慈童の物語を描いた能で、菊の持つ長寿のイメージを象徴的に表現しています。
また、民俗の面では、9月9日に「茅の輪くぐり」を行う地域もあります。茅で作った輪をくぐることで無病息災を願うというこの行事も、重陽の節句の厄除けの意味と通じるものがあります。

やよい、文化って色んな形で伝わっていくんだね。能や茶道など、今も続く伝統文化に重陽の節句の精神が生きているというのは素晴らしいことだね

うん、昔の人の知恵や美意識が、今の私たちの生活にもつながっているんだね!
重陽の節句は、日本文化の奥深さと継続性を示す素晴らしい例と言えるでしょう。現代に生きる私たちも、この豊かな文化遺産を大切に受け継いでいきたいものですね。次は、文学作品の中で重陽の節句がどのように描かれてきたのかを詳しく見ていきましょう。
俳句や童話に見る重陽の節句
重陽の節句と菊のイメージは、日本の文学作品の中に数多く登場します。特に季節を大切にする俳句では、菊は秋を代表する季語として重要な位置を占めています。
松尾芭蕉の「菊の香や奈良には古き仏たち」という句は、菊の香りと奈良の古い仏像を結びつけた名句です。また、与謝蕪村の「菊白し鐘は如法西の寺」という句は、白い菊と寺の鐘の音が織りなす静かな秋の情景を描いています。

おじいちゃん、俳句って17文字しかないのに、どうしてこんなに情景が浮かぶの?

言葉の選び方と配置が絶妙だからだよ。少ない言葉で多くを語るのが俳句の魅力なんだ
現代俳句でも菊は人気のテーマです。高浜虚子の「菊の香のかすかに残る座敷かな」や、水原秋桜子の「まなじりに菊日和かな城の辺」など、菊の美しさと重陽の節句の風情を詠んだ句が数多くあります。
童話や昔話の中にも、菊にまつわる物語があります。「菊の御紋」という童話では、天皇が菊の美しさに感動して紋章に選んだという物語が語られています。また、「菊と刀」という昔話では、侍の忠義と菊の高潔さが重ね合わされています。
明治時代の文豪、夏目漱石の小説『草枕』には、「菊には薫る魂がある」という有名な一節があります。これは菊の持つ芳香と精神性を表現したもので、日本人の菊に対する特別な感情を象徴しています。
また、芥川龍之介の短編「藪の中」では、重陽の節句の背景に物語が展開され、季節感を醸し出しています。このように、日本文学において菊と重陽の節句は、季節を表すだけでなく、象徴的な意味合いも持っているのです。

やよい、文学作品を通して季節を感じるのも、日本文化の素敵なところだね

私も国語の授業で習った俳句、今度は季節感を意識して読んでみるね!
文学の中に描かれた重陽の節句と菊のイメージは、日本人の美意識や自然観を如実に表しています。皆さんも、秋の夜長に菊をテーマにした詩や小説を読んでみてはいかがでしょうか?次は、重陽の節句に関連する茶道と着物の文化について詳しく見ていきましょう。
重陽の節句に関連する茶道と着物
重陽の節句の時期には、茶道や着物文化にも季節の移ろいが美しく表現されています。これらの伝統文化が、どのように重陽の節句と結びついているのか見ていきましょう。
茶道では、季節ごとに趣向を凝らした茶会が開かれます。9月の茶会では、菊をモチーフにした菓子がよく用いられます。「菊乃寿」や「菊づくし」など、菊の形や色を表現した上生菓子は、見た目も美しく、口に入れると秋の風情を感じられます。

おじいちゃん、お茶会の和菓子って、どうしてこんなに季節感があるの?

茶道では『一期一会』を大切にしているんだ。その日、その時にしか味わえない季節の移ろいを、菓子や茶花を通して表現しているんだよ
茶室に飾る花入れも、重陽の節句の時期には特別なものが選ばれます。竹や陶器の花入れに一輪の菊を生けるだけで、茶室全体に秋の気配が漂います。また、床の間に掛ける掛け軸も、菊や重陽をテーマにしたものが選ばれることが多いです。
着物の世界でも、重陽の節句の頃になると、菊の模様が施された着物が着られるようになります。特に、薄い生地の単衣(ひとえ)から、少し厚手の袷(あわせ)に衣替えする時期でもあり、菊の模様は秋の訪れを告げる象徴でもあるのです。
菊の模様は、着物の柄として古くから親しまれてきました。単純化された十六菊紋や菊唐草模様、写実的な菊の花びらなど、様々なデザインがあります。色も、白や黄色の他、紫や赤など豊富なバリエーションがあります。
また、帯留めや簪(かんざし)などの装飾品にも、菊のモチーフが多く使われています。菊の帯留めを付けるだけで、着物姿に秋の雰囲気が加わります。

やよい、日本人は昔から身に着けるものにも季節感を大切にしてきたんだね

今の私たちも、もっと季節を感じる装いを楽しみたいな。学校の制服でも何か小物で工夫できるかも!
このように、重陽の節句は茶道や着物文化の中にも深く根付いています。伝統文化の中に息づく季節感は、現代の私たちにも大切な感性を教えてくれるのではないでしょうか。
まとめ:私たちの生活に重陽の節句を取り入れる
重陽の節句について、起源から現代までの様々な側面を見てきましたが、いかがでしたか?今では少し影が薄くなってしまったこの節句も、実は私たちの生活に取り入れる価値のある素晴らしい伝統行事なのです。

おじいちゃん、重陽の節句って本当に奥が深いね。単なる行事じゃなくて、そこに込められた先人の知恵や願いがあるんだね

そうだよ、やよい。昔の人は季節の変わり目を大切にして、健康を願う気持ちを形にしていたんだ。その知恵は今でも十分通用するものだと思うよ
重陽の節句を現代の生活に取り入れるのは、実はとても簡単です。9月9日に菊の花を飾る、高いところに登って景色を楽しむ、菊のお茶や菊酒を楽しむ、菊をモチーフにした和菓子を味わう…。これらはどれも特別な道具や技術がなくても実践できることばかりです。
大切なのは、その行為の背景にある「健康と長寿を願う」気持ちを意識することでしょう。季節の変わり目に、家族の健康を願い、自然の恵みに感謝する。そんな心のゆとりが、忙しい現代社会に生きる私たちにはとても必要なのではないでしょうか。
また、子どもたちに重陽の節句について教えることも意義深いことです。日本の伝統文化や季節感を伝えることで、豊かな感性を育むことができるでしょう。菊の押し花作りや、菊の花を使った料理作りなど、子どもたちと一緒に楽しめる活動もたくさんあります。

やよい、このブログを読んでくれた人が、少しでも重陽の節句に興味を持ってくれたらうれしいね

うん!昔の行事だけど、今の生活に役立つ素敵な知恵がたくさん詰まってるもんね
皆さん、今年の9月9日は、ぜひ重陽の節句を意識して過ごしてみませんか?伝統行事を現代に蘇らせることで、私たちの生活がより豊かになるかもしれません。菊の花と共に、健康と長寿を祈る特別な一日を過ごしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。皆さんの暮らしに、日本の素敵な伝統文化が彩りを添えますように!















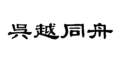
コメント